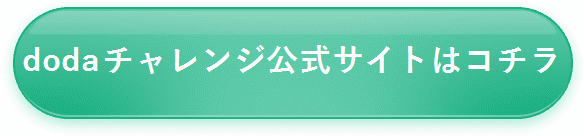dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します


dodaチャレンジに登録したのに、なんで紹介が断られるの?自分だけ?
せっかく「dodaチャレンジ」に登録したのに、「ご紹介できる求人が現在ありません」と言われてしまった経験はありませんか?エージェントに断られると、ちょっとショックですよね。でも、それにはちゃんとした理由があるんです。転職活動を前に進めるためには、なぜ断られるのかを知ることがとても大事。
この記事では、dodaチャレンジで紹介を断られる原因と、そうなってしまった時の対策を詳しく紹介していきます。落ち込むよりも、「どうすればいいか」を知って行動する方がずっと前向きですよね。
この記事を読めば、「なぜ自分はダメだったのか…」という疑問がクリアになり、次のステップに進む自信が持てるはずです。

dodaチャレンジで断られる理由がわかれば、次の行動も見えてくるね!
断られる理由1:紹介可能な求人が見つからない

どうして自分に紹介できる求人が見つからないんだろう?
dodaチャレンジでは、登録者の希望条件と企業側の求人内容がマッチしないと、紹介自体が難しいと判断されてしまうケースがあります。特に条件が厳しい、または限定的な場合、求人の幅が狭くなってしまい、なかなかマッチする仕事が見つからないことも。以下のような状況は要注意です。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
「在宅勤務じゃなきゃダメ」「年収は最低でも500万円」など、こだわり条件が強いと、その条件に該当する求人が極端に少なくなります。特に障がい者雇用では、企業側も環境整備に限界があるため、柔軟な条件で考えることがポイントです。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職)
「デザイン系がいい」「映像制作しか無理」といったように、職種を絞りすぎていると求人自体が少なくなります。特に一般企業での障がい者雇用では、こうした専門職の枠が非常に限られているため、視野を少し広げることも重要です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方にお住まいの方は、そもそも求人が少ないという地域差の壁にぶつかることも。希望勤務地を都市部にまで広げたり、通勤可能な範囲を見直すことで、紹介可能な案件がグッと増える可能性があります。

希望条件を少しゆるめるだけで、可能性は大きく広がるんだね!
断られる理由2:サポート対象外と判断される場合

どんな人がサポート対象外になってしまうの?
dodaチャレンジは、すべての人に求人を紹介できるわけではなく、一定の条件に合った人を支援する仕組みです。以下に該当する場合は、サポートの対象外とされることがあるため注意が必要です。
障がい者手帳を持っていない(障がい者雇用枠の利用には原則手帳が必要)
障がい者雇用枠での求人紹介をメインとするdodaチャレンジでは、障がい者手帳の所持が原則条件です。まだ取得していない場合は、取得の可否を専門機関に相談することをおすすめします。
職歴にブランクがあり、実務経験がほとんどない
長いブランクや経験不足は、企業が採用をためらう要因となることもあります。まずは短時間勤務や訓練を受けるなど、段階的な就労を視野に入れてみましょう。
体調が不安定で、すぐに働ける状態ではない
就職に向けた準備がまだ整っていない場合、「就労移行支援」を紹介されることがあります。まずは体調の安定が第一。焦らず、自分のペースで前に進むことが大切です。

条件を確認して、自分が対象かどうかチェックしておくのが大事だね!
断られる理由3:面談での印象や準備不足が影響している場合

面談ってそんなに重要なんだ…準備不足だとダメなの?
dodaチャレンジでは、面談で求職者の希望や適性を細かくヒアリングし、その内容をもとに求人紹介が行われます。ですが、準備不足だったり、伝えるべき情報が曖昧だと、マッチする求人を紹介してもらえない可能性が高くなります。
障がい内容や配慮事項がうまく説明できない
自分の障がいの特徴や、職場でどのような配慮が必要かをしっかり伝えることが大切です。自分に合った職場を見つけるためにも、事前に整理しておくと安心です。
仕事の希望やキャリアビジョンが不明確
「どんな仕事でもいい」というあいまいな姿勢では、dodaチャレンジ側も求人を絞りづらくなります。興味のある分野や、自分の得意なことをできるだけ明確に伝えるようにしましょう。
職務経歴をうまく伝えられない
自分の過去の職務経験を簡潔に、かつ具体的に説明することが大切です。履歴書や職務経歴書を見直し、要点をまとめておくとスムーズに話せるようになります。

面談前の準備をしっかりすれば、マッチング率も上がりそうだね!
断られる理由4:地方在住やリモート希望で求人が少ない

地方だと求人が少ないって聞くけど、どのくらい違うのかな?
勤務地の希望条件が限定的すぎると、dodaチャレンジで紹介できる求人がかなり少なくなってしまうことがあります。柔軟な対応ができると、選択肢が一気に広がります。
地方在住(北海道・東北・四国・九州など)
都市部と比べて、地方では障がい者雇用枠の求人が全体的に少なめです。通勤可能な範囲を広げたり、場合によっては転居も視野に入れることで、紹介可能な案件の幅が広がります。
完全在宅勤務を希望している
リモート勤務を希望する人が増えていますが、完全在宅の求人はまだ少数派。週に数日の出社が可能であれば、その分多くの求人にアクセスできるようになります。

ちょっと条件を緩めるだけで、チャンスがぐっと増えるんだね!
断られる理由5:登録情報に不備・虚偽がある

ちょっとぐらいならって、情報を盛るのはダメかな?
登録時の情報が不正確だったり、故意に偽っていた場合は、dodaチャレンジからのサポートが受けられなくなります。正確で誠実な情報登録が重要です。
手帳を未取得なのに「取得済み」と記載した
障がい者手帳が必要な求人にも関わらず、取得済みと記載すると、企業とのトラブルに発展する恐れがあります。誤解を生まないよう、正確な情報を記載しましょう。
働ける状態でないのに、無理に登録した
現在の体調や生活状況で働ける状態でない場合は、無理に登録してもマッチングがうまくいきません。まずは就労に向けた準備を進めることが大切です。
職歴や経歴を偽って記載した
経歴に偽りがあると、面接や企業とのやり取りで信用を失うことになりかねません。正直な記載が何よりも信頼につながります。

正直に書くことが、結果的に良いご縁につながるんだね!
断られる理由6:企業側の選考結果で不採用になる場合

dodaチャレンジで紹介されたのに、なんで不採用になるの?
dodaチャレンジから紹介された求人でも、最終的には企業ごとの選考基準によって採用・不採用が決まります。紹介されたからといって必ず内定するわけではありません。
企業の選考基準による不採用
企業によって求める人物像やスキルは異なるため、面接を通して「今回はご縁がなかった」となることもあります。複数の求人に応募してチャンスを広げることが、転職成功のカギです。
dodaチャレンジで断られた人の体験談|どうして断られたのか?リアルな声を集めました

実際にdodaチャレンジで断られた人って、どんな理由で断られているのかな?
dodaチャレンジに登録したけれど、残念ながら求人を紹介してもらえなかったという声もあります。どんな状況で「ご紹介が難しい」と判断されるのか、リアルな体験談をまとめてみました。
体験談1:障がい者手帳はあったが、スキルや資格がなく紹介NGに
これまでの仕事は軽作業の派遣が中心で、PCスキルもタイピング程度。資格もなかったため、「ご紹介できる求人がない」と案内されました。
体験談2:体調が安定しておらず、まずは就労訓練を勧められた
「継続して働けるか不明」とされ、dodaチャレンジではなく、まずは就労移行支援を利用するよう提案されました。
体験談3:長期のブランクがあり、まずは職業訓練からと提案された
精神疾患で10年以上療養していたことがあり、「まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう」と案内されました。
体験談4:地方在住&在宅希望だったが、求人が見つからなかった
四国の田舎町に住み、在宅でのライターやデザイン職を希望していたが、「ご希望に沿う求人はご紹介できません」と言われたそうです。
体験談5:正社員経験がなく、紹介は難しいと断られた
これまでアルバイトや短期派遣ばかりで、正社員経験がなかったため、「正社員求人の紹介は難しい」と案内されました。
体験談6:希望条件が多すぎて紹介不可に
子育て中で「完全在宅・週3・時短・事務職・年収300万円以上」と希望を出した結果、「全ての条件を満たす求人は紹介が難しい」と断られました。
体験談7:障がい者手帳未取得で紹介NGに
精神障がいの診断はあったものの手帳未取得の状態で登録しようとしたところ、「手帳がないと求人紹介は難しい」と断られました。
体験談8:未経験からITエンジニア希望だったが断られた
長年軽作業をしていたが、体調を考慮し在宅でのITエンジニア職に挑戦したいと相談。結果、「未経験でのエンジニア職はご紹介が難しい」と案内されました。
体験談9:通勤困難で在宅希望、短時間勤務を希望したがNG
身体障がいにより通勤が難しく、短時間在宅勤務を希望していたが、「現在ご紹介できる求人がありません」と断られました。
体験談10:高年収&管理職希望で求人が見つからなかった
前職は中堅企業の一般職だったが、今回は障がい者雇用で年収600万円以上の管理職を希望。結果、「ご紹介可能な求人は現在ありません」と言われたそうです。

体験談を見てみると、条件を見直したり、準備を整えることが大切だとわかるね!
dodaチャレンジで断られたときの対処法を徹底解説!

dodaチャレンジで断られたら…もう転職できないのかな?
dodaチャレンジから「紹介できる求人がありません」と言われてしまうと、つい落ち込んでしまうものです。「もう無理かも…」と思ってしまう人も少なくありませんが、対処法を知って行動すれば、再チャレンジは十分に可能です。
大切なのは、「なぜ断られたのか」をしっかり把握すること。そして、その理由に応じたアクションをとることが、次のステップへつながります。
この記事では、スキル不足や職歴のブランクなど、dodaチャレンジで断られる原因ごとの対処法を具体的に紹介していきます。
「断られた=終わり」ではありません。むしろ、今後の方向性を見直すチャンスと考えて、一歩ずつ進んでいきましょう。

諦める前に、自分にできることを整理して行動するのが大切だね!
スキルや職歴が足りない場合の対処法|「経験不足」で断られたら?

軽作業の経験しかないし、パソコンもあまり得意じゃない…どうすれば求人を紹介してもらえるの?
職歴が浅い、短期バイトばかり、PC操作に自信がない…という場合、dodaチャレンジから「紹介できる求人がありません」と言われることもあります。ですが、今からスキルを身につける努力をすれば、十分巻き返しは可能です!以下の方法で、経験やスキルの不足を補っていきましょう。
ハローワークの職業訓練を利用する|無料or低額でPCスキルが学べる
ハローワークでは、就職支援の一環として職業訓練を提供しています。WordやExcelの基本操作、データ入力などのPCスキルを基礎から学べるコースが用意されていて、受講料は無料またはごく低額です。事務系の仕事に就きたい人には特におすすめです。
就労移行支援を活用する|実践スキル+メンタルサポートも
障がいのある方に向けた就労移行支援事業所では、ビジネスマナーやPCスキル、履歴書・面接対策など、就職に必要な実践力をトータルでサポートしてくれます。体調面のフォローや、就職後の定着支援も受けられるため、安心してステップアップを目指せます。
資格を取得する|MOSや簿記3級でスキルの証明に
実務経験が少なくても、資格があることで客観的にスキルをアピールできます。特に、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級などは、事務系職種への応募時に好印象。dodaチャレンジでの求人紹介も受けやすくなる可能性があります。

スキルや資格を身につけることで、dodaチャレンジからの求人紹介の可能性もグッと高まるね!
ブランクが長くてサポート対象外に…そんなときの対処法

何年も仕事から離れていたけど、もう一度働きたい…そんな時はどうしたらいいの?
数年にわたる療養や離職などで就労のブランクがあると、dodaチャレンジのサポート対象外となってしまうケースもあります。でも、それは終わりではありません。今からできる「準備と実績作り」で未来は開けます。
少しずつ働く感覚を取り戻し、自信をつけていくためのステップをご紹介します。
就労移行支援を利用して、生活リズム+就労訓練
長いブランクからの再出発には、まず生活リズムを整えることが大切です。就労移行支援を利用すれば、毎日決まった時間に通所する習慣が身につき、ビジネススキルの習得や企業実習の機会も得られます。実績を積むことで、dodaチャレンジ再登録時の信頼度もアップします。
短時間のバイト・在宅ワークで働く実績をつくる
いきなりフルタイムは難しいという方は、週1〜2回の短時間勤務や、在宅でできる仕事からスタートするのも効果的です。続けることで「継続して働ける」ことを証明でき、履歴書にも記載できる実績になります。
実習やトライアル雇用にチャレンジする
企業実習やハローワークのトライアル雇用制度を活用すれば、実際の現場で働く経験を積むチャンスがあります。このような経験があると、再度dodaチャレンジを利用する際にも好印象となり、紹介の幅が広がることにつながります。

「働ける状態に近づくこと」が、再チャレンジの第一歩になるんだね!
地方在住やフルリモート希望で求人がない場合の対処法

地方に住んでいると、dodaチャレンジでは求人が見つからないのかな?どうすればいいんだろう?
都市圏と比べて、地方では障がい者雇用の求人数が限られている傾向にあります。また、フルリモート勤務を希望する場合も、対応可能な求人は非常に限定的です。
そんなときでも諦めず、以下のような方法を試してみることで、新しい可能性が見えてきます。
在宅勤務可能な求人を探す|他の障がい者専門エージェントも併用しよう
dodaチャレンジ以外にも、障がい者向けに特化した転職エージェントは複数あります。「atGP在宅ワーク」「サーナ」「ミラトレ」などは、在宅勤務求人を多く扱っており、併用することで出会える求人の幅が広がります。
クラウドソーシングを活用して、在宅で働く実績を積む
「ランサーズ」「クラウドワークス」などのクラウドソーシングサービスでは、ライティングやデータ入力など、未経験でも始めやすい仕事が多くあります。実績を積むことで、将来的に在宅勤務の正社員求人にも応募しやすくなります。
地域のハローワーク・就労支援センターに相談する
大手転職サイトに出ていない求人は、地元のハローワークや障がい者就労支援センターに相談することで見つかることがあります。地域密着型の企業情報が得られることもあり、意外な掘り出し求人が見つかることも!

地方や在宅希望でも、探し方を変えればまだまだチャンスはあるね!
条件が厳しすぎて求人紹介がなかったときの対処法

条件をいろいろ付けたら求人紹介を断られちゃった…。どうすればいいの?
「完全在宅」「週3勤務」「年収300万円以上」など、希望条件を細かく設定することで、求人の選択肢が一気に狭まってしまうことがあります。条件を見直すことで新たな可能性が開けるケースも多く、少しの柔軟性がチャンスを広げてくれます。
条件に優先順位をつける|「絶対譲れない条件」と「希望条件」を分ける
希望条件をすべて満たす求人は、正直とても少ないのが現実。だからこそ、「これだけは絶対に譲れない」条件と「可能なら満たしたい」希望条件を分けて考えることが大切です。たとえば、「完全在宅が絶対」ではなく、「週1〜2回の出社なら対応可能」と柔軟に考えると、選択肢が大きく広がることがあります。
譲れる条件をアドバイザーに再提示する|勤務時間や出社頻度などを見直し
一度紹介を断られたとしても、条件を見直して再相談することで、状況が変わることもあります。「週5は無理だけど、週4なら大丈夫」「フルリモートが理想だけど、月1出社はOK」など、譲れる条件を具体的に伝えることで、アドバイザーも求人を提案しやすくなります。
段階的なキャリアアップを見据えた戦略を立てる
今すぐ理想の働き方ができなくても、一歩ずつ目指していくことはできます。「時短勤務から始めて、体調やスキルに慣れたらフルタイムに移行」「事務職で経験を積んで、将来的に専門職を目指す」など、段階的なキャリア戦略を立てることで、無理なく理想に近づける道が開けます。

理想に近づくには、今の自分に合った条件からスタートするのが大事なんだね!
障がい者手帳未取得や区分の違いで断られたときの対処法

まだ障がい者手帳を持っていないけど、dodaチャレンジで断られたらどうすればいいの?
dodaチャレンジは、障がい者雇用枠での求人紹介が中心のため、手帳がないとサポートが受けられないケースがあります。しかし、手帳未取得の方でも取れる対策はあります。
主治医や自治体に相談して手帳取得を検討する
精神障がいや発達障がいで「手帳の取得が難しそう」と思っている方も、診断や症状によっては取得可能です。まずは主治医に相談し、自治体の窓口で申請手続きの確認をすることで、障がい者雇用枠の求人に応募できるようになります。
「手帳なしOK」の求人を探す|ハローワークや支援機関の活用
ハローワークや一部の就労支援機関では、手帳未取得でも応募できる一般枠や配慮のある求人を紹介している場合があります。また、就労移行支援を利用しながらスキルや実績を積み、後から手帳を取得してdodaチャレンジに再登録する流れも有効です。
体調の安定を優先し、手帳取得後に再チャレンジ
体調が不安定な場合は、無理に就職を急がず、まずは治療と生活の安定を優先しましょう。医師のアドバイスを受けながら準備を整え、手帳取得後に再度サポートを受けるという流れで、自分に合った働き方を目指すことができます。

まずは手帳の取得を目指しつつ、今できる準備を進めていこう!
その他の対処法|dodaチャレンジ以外のサービスを活用しよう

dodaチャレンジでダメだったら、もう終わりなの…?
もしdodaチャレンジで紹介を受けられなかったとしても、他にも多くの転職支援サービスがあります。それぞれに特徴があるため、目的や状況に合わせて使い分けることで、チャンスが広がります。
- atGP:障がい者向け求人が豊富。就職フェアや相談会も充実。
- サーナ:長年の実績があり、在宅勤務や大手企業の求人も掲載。
- ラルゴ高田馬場:訓練付きの転職支援が特徴。通所型支援にも対応。
また、地域密着型のハローワークや障がい者就労支援センターも頼れる存在です。地元企業の求人情報やサポートが受けられ、非公開求人に出会える可能性も。
大切なのは、一つの方法にこだわらずに複数の選択肢を持つこと。自分に合った方法を探し、少しずつ前に進めば、理想の就職先にきっと出会えます。

いろんなサービスを活用して、自分に合ったチャンスを見つけよう!
身体障害者手帳を持つ人の就職事情とは?精神・発達障害との違い

身体障害の人って、精神や発達障害の人と比べて就職しやすいの?
身体障害者手帳を持っている方は、精神障害や発達障害のある方と比べると、企業側が配慮しやすいという理由で就職のハードルがやや低い傾向があります。とはいえ、すべてのケースで有利とは限らず、障がいの部位や等級、通勤の可否などによって状況は異なります。
障害等級が軽度の場合は、就職の可能性が広がりやすい
身体障害の等級が5級・6級など軽度の場合、オフィスワークや軽作業など幅広い業務に対応しやすく、企業も配慮しやすいため採用される可能性が高まります。
身体障害は「配慮すべき内容」が明確で、企業側が受け入れやすい
車椅子利用や片手の不自由さなど、視覚的にわかりやすい障害であるため、企業も「どのようなサポートが必要か」を判断しやすい傾向にあります。例えばバリアフリー設備の整備や、片手でのPC作業への配慮など、具体的な対応がしやすいことが採用の後押しとなります。
合理的配慮の範囲が明確で企業側も安心できる
合理的配慮とは、障がいのある方が安心して働けるように職場環境を整える企業側の取り組みです。身体障害は配慮すべき点が明確なため、採用側も事前準備しやすく、安心して受け入れられる体制が築かれやすいです。
通勤や作業に制約がある場合は、求人の選択肢が狭まることも
上肢・下肢に障がいがある場合、階段のある職場や、手作業が多い職種には不向きなこともあります。ただし、在宅勤務や座って行える業務であれば、無理なく働ける職場が見つかる可能性が高いです。
対人コミュニケーションに問題がなければ、幅広い職種が狙える
身体障害があっても、会話や電話応対がスムーズにできる方は、営業職や事務職でも採用されやすいです。企業は「障害よりも人柄や対話力」を重視する傾向があるため、面談での印象も大きなポイントになります。
PCスキルがあれば、事務職や在宅勤務にもチャンスが広がる
身体的な負担が少ないPC業務(データ入力・経理補助・一般事務など)は、身体障がいのある方に人気があり、求人も豊富です。さらに在宅勤務が可能な企業も増えており、スキルがあれば選択肢はさらに広がります。

身体障がいの場合は、配慮が明確だから企業側も受け入れやすいんだね!
身体障害者手帳を持つ人の就職事情とは?

身体障がいがある人って、他の障がいと比べて就職しやすいって本当?
身体障害者手帳を持っている方は、精神障害や発達障害のある方と比べて、就職のハードルがやや低くなる傾向があります。これは、企業側が障がい内容を把握しやすく、必要な配慮が明確にできるためです。
ただし、障がいの程度や影響によっては、応募できる求人が限られることもあるため、自分に合った職種や働き方を見極めることが大切です。
軽度等級(5〜6級)は就職しやすい傾向
障がいの等級が軽度であれば、企業側の負担も少なく、幅広い職種での採用が見込めます。特にオフィスワークや軽作業などでは、積極的に採用する企業も増えています。
障がいの内容が「見えやすく」、配慮の方向性が明確
車椅子の利用や片手の麻痺など、具体的な障がい特性が把握しやすいため、企業側も「どのような対応が必要か」を理解しやすく、職場環境の調整もしやすいです。
合理的配慮の実施が明確にできるため企業も安心
合理的配慮とは、障がい者が働く上で必要な支援を提供することです。身体障がいはこの配慮が視覚的・物理的に明確なことが多く、バリアフリー化や補助器具の設置などもスムーズに導入されやすいです。
通勤や作業に支障があると求人は限定的になる
下肢や上肢の障がいで通勤が難しかったり、手先を使う作業に制限がある場合、応募できる職種は限られます。ただし、在宅勤務やデスクワーク中心の職種では、その影響が少なく、採用されやすい傾向があります。
コミュニケーション力があれば採用の可能性は広がる
身体に障がいがあっても、対話力やビジネスマナーに問題がなければ、営業職やカスタマーサポートなど、幅広い職種での活躍が可能です。人柄や対応力が評価される場面も多くあります。
PCスキルを活かせる職種に強み|事務職は特に人気
データ入力や書類作成などの事務職・バックオフィス業務は特に身体障がいの方に人気です。身体的負担が少なく、在宅勤務との相性も良いため、選択肢が多くなる分野です。

身体障がいがある方は、配慮がしやすい分、採用の可能性も広がりやすいんだね!
精神障害は「安定して働けるかどうか」が最重視される
精神障がいのある方が就職活動を行う際、企業が最も気にするのは「安定して継続勤務できるか」という点です。過去に長期間の休職歴や離職の繰り返しがある場合、企業側は慎重な姿勢を取る傾向にあります。
安定した勤務実績を示せるかがカギとなるため、生活リズムを整えたり、短時間から勤務を始めるなど、安定就労に向けた準備が重要です。
「見えにくい障がい」だからこそ、配慮点の明確化が必要
精神障害や発達障害は外見ではわかりにくいため、企業側は「どう接したら良いか分からない」という不安を抱えることが多いです。
そのため、応募や面接の段階で「どんな環境なら安定して働けるのか」「どんな配慮があると安心できるのか」を伝えることで、企業の理解を得やすくなります。
面接時の「配慮事項の伝え方」が採用の分かれ目になる
採用面接では、自分の障がい特性や希望する配慮について具体的かつシンプルに伝えることが大切です。
例として、「電話対応が苦手なのでメール中心の指示がありがたい」「月1回の通院が必要」「静かな職場環境が望ましい」など、働く上での「最低限の配慮」を明確に伝えると、企業側も採用の判断がしやすくなります。
一方で、過度な配慮を求めすぎると、企業側に負担感を与える可能性があるため注意が必要です。

自分の状態を正しく伝えることが、企業との良い関係づくりの第一歩だね!
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ人の就職事情とは?

知的障がいを持っていると、どんな仕事ができるのか不安…
療育手帳を持つ方の就労状況は、手帳の区分(A判定・B判定)によって大きく異なります。それぞれの判定に合わせて適した働き方を選ぶことが大切です。
療育手帳の区分によって就労スタイルが変わる
A判定(重度)は、一般企業での就労が難しい場合が多く、「就労継続支援B型」など福祉的就労が中心となります。
B判定(中軽度)は、障がい者雇用枠や一般企業での就職が現実的となり、軽作業や事務補助、清掃業務などで働く方も多くいます。
A判定の方は「無理せず働く」B型支援でスキルアップを目指そう
「就労継続支援B型」は、体力や作業スピードに配慮された環境で働ける福祉的なサービスです。無理なく通いながら、作業スキルや生活リズムを整えることができ、将来的にA型や一般就労へステップアップするための土台づくりになります。
B判定の方は企業就職のチャンスも多い
B判定を持つ方は、就労支援やアドバイスを受けながら、障がい者雇用枠のある企業に就職できる可能性が高くなります。特に、定型作業を中心とした業務(検品・梱包・清掃など)では、安定して長く働ける方も多いです。

自分の障がい特性に合わせた働き方を選ぶことで、無理なく仕事を続けられそうだね!
障がいの種類別に見る|就職のしやすさと対策ポイント

障がいの種類によって、やっぱり就職しやすさって変わってくるのかな?
障がい者雇用枠の求人においては、障がいの種類によって企業側の受け入れ体制や採用のハードルが異なるのが現実です。
一般的に「配慮しやすく、企業が理解しやすい障がい」は就職しやすくなる傾向があります。特に身体障がい(軽度)は、必要な配慮が明確であり、企業側も安心して採用できるため、選択肢が広がります。
一方で、精神障害や発達障害、知的障害(A判定)のように、支援や配慮の内容が個人差によって大きく変わる障がいは、就職にあたって事前の準備や環境整備が重要になります。
それぞれの障がいに合わせた対策をとれば、就職の可能性は大きく広がります。dodaチャレンジで断られても、他の転職支援サービスや福祉機関の活用によって、自分に合った働き方を見つけることは十分可能です。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |

障がいの特性を理解して、対策を立てることでチャンスは確実に広がるね!
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いとは?自分に合った働き方を選ぼう

障害者雇用枠と一般雇用枠って、どう違うの?どっちが自分に合ってるんだろう?
障がいのある方が就職活動を行うとき、「障害者雇用枠で応募するか」「一般雇用枠でチャレンジするか」は大きな判断ポイントになります。
それぞれの雇用枠には特徴とメリット・デメリットがあるため、自分の体調やスキル、希望する働き方に応じて選択することが大切です。
障害者雇用枠のポイント①|企業の法的義務に基づく採用枠
障害者雇用枠は、企業が「障害者雇用促進法」に基づいて設けている制度で、障がい者が働きやすい環境を整えることが前提となっています。
障害者雇用枠のポイント②|2024年4月から雇用率2.5%へ引き上げ
民間企業には、従業員の2.5%以上を障がい者として雇用する義務があります(2024年4月より)。このため、多くの企業が積極的に障がい者を採用しており、安心して働ける制度が整っています。
障害者雇用枠のポイント③|配慮事項を伝えたうえで採用される
障がい者雇用枠では、自分の障がいや働きやすい環境について事前に企業へ伝えることで、必要な配慮(例:通院・作業ペースの調整・静かな職場環境)を受けやすくなります。
一般雇用枠のポイント①|障がいの有無に関係なく平等な競争
一般雇用枠は、障がいのある・なしに関係なく、全員が同じ基準で採用される枠です。実力やスキルが重視され、特別な配慮を求めることは基本的にできません。
一般雇用枠のポイント②|障がいの開示は本人の判断に任される
一般枠では、「障がいがあることを伝えるかどうか(オープン or クローズ就労)」を自分で選ぶことができます。配慮を求めたい場合はオープン就労を選ぶのが一般的です。
一般雇用枠のポイント③|原則として配慮は受けられない
一般枠での就労では、障がいに関する特別な対応は想定されていないのが前提です。定期的な通院・勤務時間の調整・業務内容の配慮などが必要な場合は、事前に話し合いができる職場を探す必要があります。

自分の特性や働き方に合わせて、どちらの雇用枠が合っているかをしっかり見極めたいね!
年代によって就職のしやすさは違う?障がい者雇用と年齢の関係性

年齢が上がると、障がい者雇用ってやっぱり不利になっちゃうのかな?
障がい者の就職活動においては、年代によって採用のしやすさに違いが出るというのが現実です。
特に20〜30代は未経験可の求人も多く、将来性を評価されやすい傾向があります。一方で40代以降になると、「即戦力としてのスキル」や「過去の職歴」が重視されるため、難易度が高まることがあります。
2023年「障害者雇用状況報告」では、雇用率は2.3%と過去最高に
厚生労働省の統計によると、民間企業における障害者雇用率は2023年時点で2.3%と上昇傾向にあり、2024年4月からは法定雇用率が2.5%へ引き上げられます。
これにより、企業側の採用枠が増えるため、今後さらに就職のチャンスは広がる見込みです。
若年層は採用率が高め|未経験やスキルアップ前提の求人が豊富
20代〜30代はポテンシャル採用が多く、企業も育成前提で採用することが一般的。そのため、障がいがあっても働きやすい環境が整いやすいのが特徴です。
40代以降は「職歴」と「即戦力性」が重視される
中高年層では、過去の経験やスキルの有無が重要視されるため、求人の選択肢は絞られる傾向があります。特に未経験職種への転職は難易度が高くなります。
年齢が高くても「スキル」「在宅勤務」「専門性」で突破口あり
PCスキルの習得や資格の取得、在宅勤務可能な職種に絞って対策することで、年齢の壁を乗り越えることも可能です。50代以上での採用実績も増えてきています。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職・転職が中心。未経験OKの求人が豊富。 |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す層。経験を活かした採用が増える。 |
| 40代 | 約20~25% | 職歴により採用の幅が変化。未経験はやや厳しい。 |
| 50代 | 約10~15% | 採用枠は少なめだが、経験者・専門職ならチャンスあり。 |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務中心での就業が多い。 |

年齢に関係なく、「準備」と「戦略」で就職のチャンスは掴めるんだね!
【年代別】障がい者雇用の実態とは?年齢によって変わる就職の難易度

年齢が上がると、障がい者の就職ってやっぱり不利になってしまうのかな…?
障がい者雇用においては、年齢によって就職のしやすさが変わる傾向があります。特に20代〜30代の若年層は、未経験でもチャレンジしやすい職種が多く、企業側も将来性を重視して採用する傾向があります。
一方で40代以降になると、「即戦力」や「専門スキル」が求められるケースが増え、就職難易度が高くなることも。しかし、スキルの習得や働き方の工夫で、年齢に関係なくチャンスを掴むことは可能です。
最新統計|障害者雇用率は上昇傾向に
厚生労働省の「障害者雇用状況報告(2023年)」によると、民間企業の障害者雇用率は約2.3%と過去最高を記録。2024年4月以降は法定雇用率が2.5%へ引き上げられる予定で、企業の採用枠も拡大していきます。
20代〜30代は採用されやすく、未経験歓迎の求人も豊富
若年層は「今後の成長」や「柔軟な働き方」に期待されやすく、事務職や軽作業系など未経験OKの求人も多く見られます。就労移行支援を活用してスキルを身につけることで、さらに選択肢が広がります。
40代以降は職歴や専門性がカギに
40代を過ぎると、企業側は「即戦力として活躍できるか」を重視する傾向が強まります。これまでの職歴をアピールできる求人や、PCスキル・資格取得を通じて専門性を高めることが就職成功のポイントです。
50代以降は短時間勤務や在宅ワークが選択肢に
50代以上では、体力や勤務時間の制限を考慮した求人(清掃・軽作業・在宅事務など)が中心となります。特に近年は在宅ワークの求人も増えているため、PCスキルを活かして無理なく働ける環境を探すことが大切です。
| 年代 | 採用傾向 | 特徴とポイント |
|---|---|---|
| 20代 | 採用されやすい | 未経験OKの求人が多く、成長前提での採用が中心 |
| 30代 | やや有利 | 経験や安定性を評価されやすい。転職者も多い |
| 40代 | やや厳しい | 職歴やスキルがないと選考通過は難しくなる |
| 50代 | 限定的 | 短時間勤務・特定業務が中心。在宅勤務に活路あり |
| 60代 | 非常に少ない | 再雇用・嘱託・軽作業が主流。定年後も工夫が必要 |

年齢が上がっても、自分のスキルや働き方を工夫すればチャンスはあるんだね!
就活エージェントに年齢制限はある?dodaチャレンジの年齢対象をチェック!

エージェントって年齢制限があるの?50代や60代でも利用できるのかな?
dodaチャレンジなどの障がい者向け就活エージェントは、基本的に公式な年齢制限は設けていません。しかし、実際のところ求人紹介の中心は50代前半までの年代がメインターゲットとなる傾向があります。
企業側が「長く働ける人材」や「今後の成長性」を重視するため、20代〜50代前半までの求職者にマッチしやすい求人が多いのが現実です。
年齢制限はないが、実質的に50代前半までが中心
60代やそれ以上の求職者でも登録自体は可能ですが、紹介される求人の数が少なくなる傾向があります。とはいえ、経験を活かした専門職や短時間勤務の求人など、選択肢はゼロではありません。
50代以降は「併用戦略」でチャンスを広げよう
dodaチャレンジだけに頼らず、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センターなど、公共の就労支援サービスを併用することで、年齢や状況に合った求人に出会える可能性が高まります。
特に以下の機関はおすすめです:
- ハローワーク障がい者専門窓口:地域密着型の求人多数、年齢制限なし
- 障がい者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構):職業評価・職場実習などの支援が充実
こうした支援機関では、個別面談・職業訓練・職場実習などのプログラムを通じて、就職に向けた準備を進められるのも魅力です。
dodaチャレンジなどのエージェントサービスを活用しつつ、公的支援と組み合わせて「自分に合った働き方」を模索することが、長期的な就業のカギになります。

年齢が高くても、エージェント+公的支援でしっかり選択肢を広げていこう!
dodaチャレンジの口コミって実際どう?利用前に気になる疑問をチェック!

実際に利用した人の感想や、よくある不安ってどんなことがあるの?
dodaチャレンジを検討中の方にとって、「口コミや評価ってどうなの?」という疑問はとても気になるポイントですよね。また、「登録したけど断られた…そんな時はどうすればいいの?」という声も少なくありません。
このセクションでは、dodaチャレンジに関して多くの方が抱くよくある質問(FAQ)を分かりやすく解説していきます。
疑問を事前に解消することで、安心してサービスを利用できるようになります。あわせて、詳しい情報が掲載されている関連ページへのリンクも紹介していますので、気になるテーマがあればぜひチェックしてみてくださいね。

利用前に「よくある質問」をチェックしておけば、不安も減ってスムーズに進められるね!
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの利用者からは、「求人の紹介がスムーズだった」「カウンセリングが丁寧だった」といった良い口コミがある一方で、「希望する求人がなかった」「面談後に連絡が来なかった」といった意見もあります。
実際の口コミや評判について詳しく知りたい方は、以下の関連ページを参考にしてください。
関連ページ:dodaチャレンジの評判は?障害者雇用の特徴やメリット・デメリットを詳しく紹介
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われたり、登録を断られたりすることもあります。しかし、原因を理解し適切な対策をとることで、再びチャンスを得ることは可能です。
例えば、スキル不足が理由なら職業訓練を受けたり、他の障がい者向け転職エージェントを併用するのも方法の一つです。詳しい対処法は、以下の関連ページで解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジはなぜ断られる?難しいと言われる理由や対処法、体験談を解説
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジの面談を受けた後、「連絡が来ない…」と不安に感じる方もいるかもしれません。
面談後に連絡がない理由として、求職者の希望条件とマッチする求人が見つからない、企業との調整に時間がかかっている、または連絡の行き違いなどが考えられます。
具体的なケースや対処法については、以下の関連ページで詳しく紹介しています。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡が来ないのはなぜ?面談・求人・内定ごとの理由と対処法を紹介!
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、職務経験や希望条件、障がいの特性、必要な配慮などについて詳しくヒアリングされます。
事前に準備しておくと、スムーズに対応できるため、面談の流れや聞かれることを事前に確認しておくと安心です。
関連ページ:dodaチャレンジ面談攻略!内定までの道のり、準備から注意点・対策まで完全網羅
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者の転職支援に特化したエージェントサービスです。
登録すると、専任のキャリアアドバイザーが付き、求職者の希望や適性に合った求人を紹介してくれるのが特徴です。企業とのマッチングや選考対策、面接の調整などのサポートも受けられるため、転職活動を効率的に進めることができます。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジの求人は、基本的に「障がい者雇用枠」が対象となるため、障がい者手帳を持っていない場合は紹介が難しくなることがあります。
ただし、手帳の取得を検討している場合は、アドバイザーに相談することで、手続きに関するアドバイスを受けられることもあります。
関連ページ:dodaチャレンジは障害者手帳なしで利用可能?必須条件や申請中の対応について紹介!
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関係なく登録が可能ですが、支援の対象外となる場合があります。
例えば、長期間のブランクがあり職歴がほとんどない場合や、体調が不安定で継続勤務が難しい場合は、就労移行支援を勧められることもあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、担当のキャリアアドバイザーに連絡するか、公式サイトの問い合わせフォームから手続きを行うことができます。
退会の際は、今後の転職活動に影響がないよう、事前に確認しておくと良いでしょう。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン(電話・Web面談)で実施されることが一般的です。
また、対面での相談を希望する場合は、拠点があるエリアでの面談が可能なこともあるため、事前に確認すると良いでしょう。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには公式な年齢制限はありませんが、実際には50代前半までがメインの対象となっています。
50代後半以降の求職者は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターを併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でもdodaチャレンジに登録し、転職活動を進めることができます。
ただし、直近の職歴がない場合やブランクが長い場合は、紹介される求人が限られることがあります。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは基本的に「転職エージェント」のため、新卒向けの求人は少なく、学生の利用は難しい場合があります。
就職活動を進める際は、大学のキャリアセンターや新卒向けの障がい者就職支援サービスを併用すると良いでしょう。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?他の障がい者向け就職サービスとの違いを比較!

他のサービスと比べて、dodaチャレンジはどんなところが違うのかな?断られることもあるって本当?
dodaチャレンジの利用を検討している方の中には、「求人を本当に紹介してもらえるの?」という不安や、「他の就職支援サービスとどう違うのか知りたい」という疑問を抱く方も少なくありません。
実際、希望条件や現在の状況によっては、求人紹介が難しくなったり、登録を断られるケースもあるのが現実です。
ただし、それはdodaチャレンジに限ったことではなく、他の障がい者向け転職サービスでも同様のことが起こり得ます。
このセクションでは、dodaチャレンジの特徴やサポート内容を解説しながら、他の障がい者就職支援サービスとの違いを比較していきます。
それぞれのサービスの得意分野を知ることで、「自分に合った就職支援」が見つかるはずです。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |

サービスごとの違いを理解して、複数併用するのが成功のコツだね!
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ

結局、dodaチャレンジで断られてしまったときはどうしたらいいの?
dodaチャレンジでは、障がいや就労状況に応じて「紹介できる求人がない」と言われたり、登録を断られてしまうケースが一定数存在します。しかし、それはdodaチャレンジに限った話ではなく、他の障がい者向け転職サービスでも状況により似たような対応がされることがあります。実際の体験談では、スキル不足や希望条件の厳しさ、体調面の不安、ブランクの長さ、障がい者手帳の未取得など、さまざまな理由で紹介が難しいとされた声が見られました。
とはいえ、そこで諦める必要はありません。職業訓練や就労移行支援、ハローワーク、他の就職支援サービスの併用など、選択肢は数多く存在します。また、公式のFAQでは、登録から面談・退会までの詳細がまとめられており、サービスの全体像を掴むのに役立ちます。
求人紹介が難しいと感じたときこそ、自分の希望条件を見直したり、ステップアップのための準備期間と捉えて行動することが大切です。dodaチャレンジのサービスを最大限に活用しながら、必要に応じて他の支援機関と連携することで、より自分に合った転職活動が進められるようになります。
まずは自身の状況を正しく把握し、無理のない目標設定と段階的なキャリア構築を意識することが、障がい者雇用での就職成功への第一歩です。

断られても大丈夫。大切なのは「次の一歩」を踏み出すことだよ!